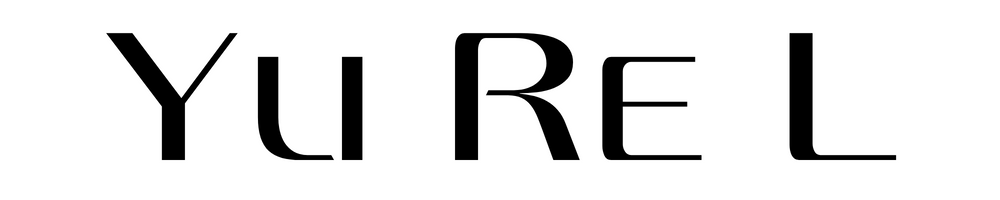暑い日々が続いているのでせめて目だけでも涼しげな世界を味わいたい。ということで、今月は20世紀美術に受けた新しい扉を開いた男「ジョルジュ・スーラ」の絵を紹介します。
無数の「点」を並べて絵にする【点描技法】を編み出し、新印象派主義という時代を作ったスーラ。
彼は31年間という短い生涯で素描(デッサン)や油絵を描きまくり、色彩現象を分析。人の網膜を利用して絵を完成させるという表現を見つけた科学者のような人物です。
では、彼の点描画の大作「アニエール水浴」について解説していきます。

東京都在住。30代で新しくできたあだ名は”分析”。趣味は人間観察、苦手なことは頑張ること。noteはじめました。
ジョルジュ・スーラのプロフィール
1859年に、パリの裕福な家庭に生まれたジョルジュ・スーラ(Georges Seurat )。
内向的で家族とさえ距離を置く父と、心優しい母のもと末っ子として育ちます。スーラは感受性が強く、無口で内気な少年でした。

中学時代からデッサン学校に通い、のちにパリの美術学校エコール・デ・ボザールへ進学。古典的な絵画を学びますが、兵役によって1年余りで中断。その後、学校は辞め、アトリエにこもって独学で印象派作品の研究を始めました。
やがて、絵の具を混ぜずに「点」で色を並べるという新しい技法を生み出します。これがのちに“点描画法”と呼ばれ、新印象派の幕開けとなるのです。
1883年、24歳のときに描いたデッサン『アマン=ジャンの肖像』がサロンに初入選を果たします。

同年、大作『アニエールの水浴』を完成させます。翌年、同作をサロンに出展するも落選し、独立展「アンデパンダン展」で披露しました。
そこでスーラに強い感銘を受けたのが、若き画家ポール・シニャックでした。彼はその後、スーラと並ぶ点描画の代表的存在となります。

そして、1885年の秋にカミーユ・ピサロと出会い、1886年には『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を第8回印象派展に出展。当時の印象派画家たちは各々好きなように絵を描いており、方向性を見失いかけていました。そんな状況で、現れた点描技法は印象派展を率いるピサロにとって“救世主”のような存在でした。
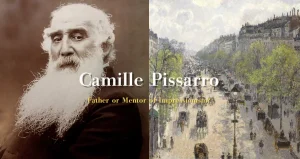

この展覧会を訪れたフィンセント・ファン・ゴッホも、スーラの絵に影響を受け、何点か点描技法の作品を残しています。


しかしスーラは真似されることを嫌い、常に“自分だけの表現”を追い求めました。
仲間の数が増えればオリジナリティは減るだろうし、皆がこの技法を使う日が来れば価値は失われ、これまでもそうだったように、何か他のものが探し求められるだろう
ジョルジュ・スーラ
晩年は夜の街やショー、サーカスに魅せられ、そのきらめく光と雑踏を見事に「点」で描き出しました。

1889年、30歳のスーラはマドレーヌという女性と恋に落ち、翌年には息子ピエールが誕生します。

そして1891年、展示会に出品するために作品の制作途中で風邪をこじらせ、ジフテリアという感染症を引き起こし、亡くなります。わずか31歳でした。
内気で無口な少年は、歳を重ねて秘密主義になっており、マドレーヌや息子の存在を家族や友人に知らせていませんでした。そして、死の2日前にようやく周囲に紹介したといいます。そしてスーラの死の2週間後、幼い息子も同じ病で亡くなります。(当時マドレーヌは二人目の子供を宿していましたが、出産前後のタイミングで亡くなってしまったようです。)
スーラの最後の超大作《サーカス》は、未完成の状態では友人たちの手によってアンデパンダン展に展示され、彼の弔いと遺志の証となりました。

「アニエール水浴」を深掘り解説
『アニエール水浴』では人物を絵の具の厚塗りで描き、夏の光や空気感を表現する部分で点描の技法を用いています。
「補色を隣り合わせに置くと、より明るく見える」という理論に基づいて描かれた本作は、スーラが見つめていた19世紀の風景や人々の姿が静かに浮かび上がります。
「アニエール水浴」を完成させるまで
本作品はスーラが初めて完成させた点描画による縦2m×横3mの超大作です。
彼の点描画の特徴は、「点を入れるのは最後の仕上げ」という点にあります。完成までに異常なまでの工程を経ており、その緻密さは群を抜いています(晩年になるとこのプロセスは少し変化していきます)。

この作品では、構成を決めるために少なくとも10点のデッサンと、14点の油彩スケッチ(いずれも15cm×25cmほど)を制作。
何ヶ月も同じ場所に通い、岸辺の人々や水浴を楽しむ姿や、全体の色彩を中心とする構成を検討するために、小さなキャンバスにまるでメモをとるように描き留めていきました。
そうして積み重ねたスケッチをもとに、最終的な構図・色彩を決定した油彩画がこちらです。

ただし、最終的な構成と言ってもモチーフ・配置・色彩の関係が決まっただけなので、人物の大きさの比率はバラバラになって遠近感がないです。
ここまで決まったら次はモデルを使って、またデッサンをして細部まで固めていくのです。
「アニエール水浴」で表す貧富の差
『アニエールの水浴』は、河畔でくつろぐ労働者たちの姿を描いた作品です。

登場人物たちは麦わら帽子をかぶっていたり、脱ぎ捨てていたりすることから、労働者階級であることが読み取れます。彼らはほとんどが背中を丸めていて、顔色もあまり良くないです。疲れた様子を感じますね。
一方、寝そべっている男性は山高帽をかぶっていることから労働階級ではなく、ブルジョワ(中産階級)ということがわかります。おそらく、職場的に偉い立場にいる方です。
彼らの手前の川には一艘の船が浮かび、目を凝らすと日傘を差す女性と、シルクハットをかぶった男性の姿が見えます。

よく見ると、その船は工場の方向から離れ、反対側へ漕ぎ出しているのです。
つまり、労働の地から余暇の地(=グランド・ジャット島)へ向かっているようにも解釈できます。
「アニエール水浴」の船が向かった先
スーラはその2年後、1886年に第8回印象派展で『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を発表します。
この舞台が、この船の“向かった先”だったのです。

島に集う人々は、日傘を差した女性やシルクハットの男性など、明らかに上流〜中流階級の人々。背筋は伸び、動きは抑えられ、彼らからは余裕と教養を感じさせる静けさが漂っています。
超大作が2部作で、こんなに工程をかけて一つの作品を描いているなんて、スーラの底知れぬなんかちょっと気持ち悪さを感じます。
ジョルジュ・スーラの作品はどこで見れる?
「アニエールの水浴」はナショナル・ギャラリー(ロンドン)で

本作品はロンドンのナショナル・ギャラリーで鑑賞できます。
ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、カラヴァッジョといった西洋絵画の巨匠たちをはじめ、印象派ではセザンヌ、ルノワール、モネ、ゴッホ、モリゾらの名作も所蔵。
さらに、イギリス国民が「最も好きな絵」に選んだ、ターナーの《戦艦テメレール号》も公開されています。

スーラの作品が多いのはオルセー美術館

パリのオルセー美術館には、スーラの最後の作品「サーカス」を鑑賞できます。
また、『アニエールの水浴』の習作の一部をはじめ、スーラの点描画や油彩、デッサンなどが数多く所蔵されています。
そのほかにも魅力的な作品がたくさんある印象派好きにはたまらない美術館ですので、展示作品や来館時の注意点などは、ぜひ以下の記事をご覧ください。

日本国内でスーラの作品を鑑賞できる場所
スーラの作品に出会える美術館は3ヶ所あります。
| 美術館 | 場所 | 展示作品 |
| ポーラ美術館 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 小塚山1285 | グランカンの干潮 |
| メナード美術館 | 愛知県小牧市小牧5丁目250 | アンサンブル(サーカスの客寄せ) |
| ひろしま美術館 | 広島県広島市中区基町3−2 | 村はずれ |
また、2025年10月25日から開催される展覧会「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」では、スーラ作品の出展は今のところ未定ですが、オルセーに所蔵されている《サーカス》が来日すれば、とてもアツいですね。
【最後に】スーラは自分の「美」を追求しまくった研究者
スーラのことを考えていると、「天才とは1%のひらめきと99%の努力」って、こういうことかもしれない…と思ってしまいます。
好きな絵をさまざまな角度からとことん研究し、「どう見えるか」ではなく「どう在るべきか」を描こうとしていたように見える彼。
「自分の中の理想」というひらめきに対して、惜しみない努力を重ねている。でもその努力も、観察と内省を繰り返す完璧主義の彼にとっては、“努力”とさえ思っていなかったのかもしれません。
彼の残した絵には、「こうであってほしい世界」への、静かな情熱が刻まれているように感じます。
参考文献
「スーラ 点描画を超えて」- 米村典子
「細部から読み解く西洋美術」 – スージー・ホッジ
「めちゃくちゃわかるよ印象派」 – 山田五郎