宮崎駿による全編オールカラーの絵物語(挿絵がメインの小説)「シュナの旅」をご存知でしょうか。
漫画版「風の谷のナウシカ」連載が始まった翌年の1983年6月に発刊されていますが、ナウシカやもののけ姫、ラピュタの原案とも言える作品です。
内容はジブリ映画と比較して”暗め”と評価されていますが、非常に宮崎駿らしいリアリティとロマンが重なるストーリーです。さらに宮崎駿の「働く」ことへの哲学や「人間讃歌」がそっと織り込まれているので、ジブリ好きには刺さるはず。
「シュナの旅」のあらすじや見どころを紹介しつつ、他のジブリ作品との関係性を考察してみました。
「シュナの旅」のあらすじと見どころ
-1024x682.jpg)
いつのころかもはや定かではない、はるか昔、あるいは遠い未来、古い谷の底に見捨てられた小国があった。そこは作物の育たない貧しい土地。その国の王子・シュナは、旅人から遠い西の彼方に黄金の穀物が豊穣になる土地があると聞き、旅へ出ることに。外の世界は犯罪が横行し、主な取引商品は”人間”であった。そんな荒涼とした世界で、シュナは”神人の土地”を見つけ、黄金の”生きている種”を見つけるが…。
あらすじ冒頭で感じる方がいるかもしれませんが、めちゃめちゃナウシカらしいSF要素も混ざった物語です。
貧しい谷の底にある土地という設定に加え、古代なのか世界が崩壊した未来なのかわからない時代。途中で出会う奴隷のテアは、容姿や性格がナウシカとシータを足して割ったような少女です。さらには、あの「ヤックル」も登場。多くのシーンで、ジブリ作品の原点を感じられて、それだけで楽しめます。
絵からは、宮崎駿らしい”大地の香り”がしてきて、その世界観に冒頭1ページ目から引き込まれます。ちなみに152ページ全編フルカラーという見応え…!
-1024x682.jpg)
さて、物語としての見どころですが、個人的には「救いが”ほぼ”ない世界」という重厚感にあると思います。そのため”暗い”と言われてしまいますが、この重々しさこそ現実のリアリティさではないでしょうか。
※以下からネ少しタバレを含みます
「シュナの旅」の世界では、人間の住む土地はいずれも貧しく、食べられる植物は育たちません。結果的に神人という存在へ人間を差し出すことで、対価として穀物を手に入れています。そのため、人狩りが横行する世界。
シュナは黄金の「生きている種」を手に入れますが、世界全体は貧困にまみれ、神人という存在も変わらず存在します。物語も9割近くが重い話で、人によっては爽快感が足りないなんて思うかもしれません。
しかし、よくある正義が悪者をこらしめるという単純構造ではないのがジブリの、宮崎駿作品の醍醐味ではないでしょうか。そんなリアリティさが作品の魅力であると同時に、美しく厳しい自然の情景、太古の生物や人喰い鬼がいる世界での冒険といったロマンに溢れています。
ナウシカやもののけ姫など絶望が支配しつつも、最後の最後にほんの少しの光が見えるくらいの作風が好きな人にはおすすめです。
「シュナの旅」はナウシカの前日譚?
ジブリ作品の面影が多数あることもこの作品の楽しみの一つで、考察がいがあります。最も色濃く世界線が共通しているのは、「風の谷のナウシカ」。
「生きている種」がある神人の土地には、漫画版ナウシカに出てくるヒドラのような存在がいたり、神人はまるで「墓所」のような建造物の姿をした生物だったり。またその土地には遺伝子操作で生み出されたのか、人間の手が及ばない場所だからなのか、太古の生物が棲みついていたりします。
そう、まるでナウシカの世界になる前のようです。さらにその想像を膨らませるのが、シュナが谷の底に住む一族であるということ。最後のカットでは、シュナとテアが谷を目指して終わりますが、もしかしたら彼らがナウシカの先祖だったり…?
また同時にラピュタのその後なのでは?と思わせるシーンがあります。それは、この大きな木でできたような船。

「天空の城ラピュタ」好きの皆さん気づきませんか? あのオープニングで出てきたラピュタ人の大きな船に酷似していることに。

しかし、「シュナの旅」では、この大きな船は地上にあり、崩壊しています。このことから「ラピュタ→シュナの旅→ナウシカ」という時間軸があるのではないか?と推測されます。
もちろん、これはそういった繋がりを求める憶測にすぎません。これらの作品は最も近い時期に作られたので、宮崎駿の想像する産物たちが酷似していても不思議ではありません。
ただこんな接続性が本作の魅力でもあるので、ジブリ作品が好きな人は、端々に転がるシーンで「これは!あの!」という発見をしてみると楽しいはずです。
「シュナの旅」に影響を与えたであろう3つの作品
私は、宮崎駿に関する書籍が好きで色々と読み漁っているのですが、彼が影響を受けたと語っていた本が「シュナの旅」の制作においてもエッセンスとして潜んでいると感じました。
それは以下の本です。
「犬になった王子」 – チベット民謡
「ゲド戦記」 – アーシュラ・K・ル=グウィン
「栽培植物と農耕の起源」 – 中尾佐助
まず、「犬になった王子」は、宮崎駿本人が「シュナの旅」の元にした話と明かしています。話としても完全に構成が一致しています。
「犬になった王子」のあらすじ
貧しい国の王子が、民を飢えから救うために、命の穀物の種を求めて旅に出るお話です。竜王から麦の粒を盗み出した結果、王子は犬の姿に変えられますが、一人の娘の愛によって救われ、ついに祖国に麦をもたらすというお話です。
「ゲド戦記」は宮崎駿が枕元に置いておくほど好きであったファンタジー小説の金字塔。私も幼少期読んで好きでした。これは「世界の均衡」と自分自身の「影」という内面との対話がテーマ。明確にこのシーンがそうだ!というわけでは無いのですが、「シュナの旅」全体に現れている静かで重い精神の旅といった雰囲気に近いものを感じました。
さらに調べてみたところ、ジブリの鈴木敏夫さんが「シュナの旅」の根底にある思想は「ゲド戦記」と明言されていました。(2015年9月23日NHK FM)
そして最後が、中尾佐助の「農耕の起源と栽培植物」。生活・社会・文化がどう変わったかを、植物の視点から読み解く本です。これは特にもののけ姫やトトロへの影響度が高かったことで知られています。
宮崎駿の「出発点」でもその影響度が何度か語られています。

読み進むうちに、ぼくは自分の目が遥かな高みに引き上げられていくのを感じた。風がふきぬけていく。国家の枠も、民族の壁も、歴史の重苦しさも足元に遠ざかり、照葉樹林の森の生命のいぶきが、モチや納豆のネバネバ好きの自分に流れ込んでくる。——自分が何者の末裔なのか教えてくれたのだった。ぼくにものの見方の出発点をこの本は与えてくれた。歴史についても、国土についても、国家についても、以前よりずっとわかるようになった。(宮崎駿 「世界、臨時増刊 岩波書店」 一九九八年七月刊)
こちらも「ゲド戦記」同様に明確にシーン反映されているものでありません。ただ「栽培植物と農耕の起源」には、栽培植物は「人類と自然の共進化」の証である話があります。宮崎駿が「命の種」をめぐる農耕を主とした話に興味を持ったこと自体に、影響が現れているのではないかと想像できます。
宮崎駿の哲学がつまった一冊をぜひ
-1024x682.jpg)
宮崎駿の教養は圧倒的です。そのためこの作品に散りばめられたテーマも一つではなく複数感じました。
その中でも個人的にいいなと感じたのは、「仕事(生活)」をする人にも焦点を当てている点。シュナの旅がメインではありつつ、少女テアがとても献身的に仕事をして妹や精神を病んでしまったシュナを支えます。黙々とひたすらに働き続ける様が、私が一番感動したシーンです。
Spotifyのポッドキャストで、「営業とサブカル」さんが語っていた「冒険をする人の英雄性」と「仕事(生活)をする人の英雄性」という言葉がとてもしっくりきました。
「冒険をする人の英雄性」に目がいきがちですが、このように日々の生活をするために仕事を懸命にこなすことへの英雄性も絵で語ってくれる、そんな素晴らしい作品です。まだ読んだことのない人は是非手にとってみてください。

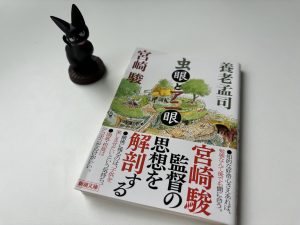
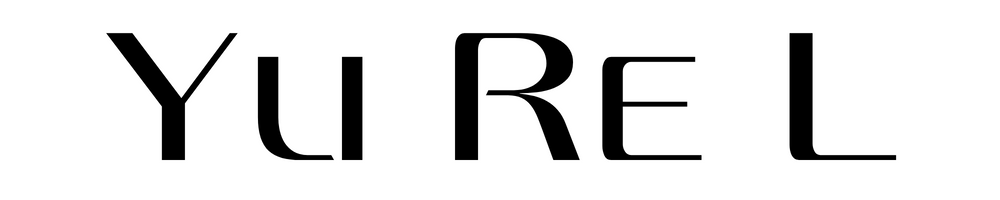
-scaled.jpg)

-300x200.jpg)